以下の抜粋は、石川県教育研究集会理科分科会で共同研究者として参加したときに配付した資料である。もうずいぶん前の著書にもかかわらず,未だ,日本の理科教育界には本書の指摘が有効である。理科教育ではなく科学教育をしていきたいものである。
Ⅰ章 理科教育の方法論(道家達将)
■文字またはことばによる人為的押しつけによってでなく,自然(物)から発見的に事物の関連を法則的に知る学習の積み重ねによって,はじめて,子どもたちは発展性ある自然科学を,その身につけることが可能となる。(二つの誤った方法,9p)
■公教育において重要なことは,日常生活のなかでは,複雑でありながら部分的に片寄った形で行なわれる経験を,より単純で基本的な経験に分解し,その中で,要素として重要なものを選んで経験させ,その経験を単に一つの経験に止めず,短時日に着実に普遍的法則の発見に発展させることである。(同上,10p)
■理科教師たるもの,その困難な条件の中で,困難であるがゆえにこそ,三つの仕事を同時に進めなければならない。すなわち,自然科学を戦争に使わせることに反対し,全人類の幸福の獲得のために発展させる仕事,教師の労働条件を改善する仕事,そしてすぐれた科学教育としての理科教育を実践する仕事と。(古くて新しいもの,19p)
Ⅱ章 理科教育論の発展(久保田芳夫)
■身近な現在見られるあれこれはいわば特殊的であり,例学的要素をあまりにも多く含みすぎるものが多いし,ものによっては生徒たちが社会に出る頃には,昔ばなしの中にのみ存在するものになってしまうのである。(教科書内容の変遷,31p)
■「身近なものや現象は複雑で,わかっていない(科学研究の上でわかっていない)ことが多い。またわかっていても,子ども特に低い学年の子どもほど,それを説明し理解させ難いことが多い」といわれた湯川秀樹博士の岡山教研での話を記憶しておきたい。(日常生活中心主義,35p)
■だから,一つの現象にぶつかった50名の子どもは,いわばそのまま50通りの問題意識を持つ(どうしたらよいかわからないというものも含めて)であろう。それをどうまとめるのか。Aは中学で,Bは来年に,Cは高校で…と多くの子どもの問題意識を切り捨てざるを得まい。すなわち子どもの自主性を尊重し,主体的活動を重視するかに見えながらこれはまさに押しつけ学習に陥らざるを得ない必然性を伴ったのである。(問題解決主義,37p)
■違う法則のからみ合ったままの現象の迷路に子どもを踏みこませるのでなく。複雑な現象の中につらぬかれる太い幹をこそ学ばせねばならない。それは自然の構造と法則性を反映する自然科学の体系と,子どもの自然認識の順次性とに基礎を置いた系統的な筋道だった学習による以外にないのである。その道筋にそって進むある段階で,それに見合って準備されたある問題が解決されるようになるということの発展の中にこそ,真の意味の「問題解決」の可能性の増大が期待されるのである。(同上,38p)
■ところが,何のために,どのような体系で,何を理解させるためにそれ(引用者註:知識や実験技術)が必要なのかということ,そしてその全体の中で位置づけといった点についての基本的な観点の方はほとんど見失われているように思える。いわば博識-博物学が前面に出てしまって,自然科学の全体的本質的把握とうう土台が忘れられているともいえる状況がそこに現出しているのである。(技術至上主義,43p)
■実証主義は「目に見える・ありのままの事実・現象」に密着するがゆえの強固さを持つ,が,それゆえに「現象」にとどまらざるを得ないし不可知論と結びつく可能性を多分に持っている。原子や宇宙や進化の考えを物質・自然を追求する理科での学習内容から排除しようとする思想-わが国の文教行政・理科教育の「主流派」の思想-はそのことと固く結びついている。(同上,46p)
Ⅲ章 理科教材の構造とその構成(細谷純)
■ここでいったい,“わかる”とは何か。上田薫は,きわめて哲学的に,「わかるとは,わからなくなることである」という。
「ふつう人びとは学問が進めば進むほど既知が増大し未知が減少すると考える。わからないことがへって,わかったことがふえると考える。しかし真実は既知が増すにしたがって未知もまたいっそう増大するのである。『わかればわかるほど,わからないことがふえる』のである。科学の進歩は,人間にますます多くの疑問をつきつけることになるのである」
(自然を改革するための行動原理としての科学・教材・学力,61p)
■小学校の理科授業でよく見られるいわゆる「実験」が,果たして本来の意味で「実験」といいうるかどうか。私には懐疑的である。ただの「実演(デモンストレーション)であったり,「観測」にすぎなかったりする場合が多いのではなかろうか。
実験器具を並べて演出効果をねらい,水の電気分解の現象をみせられても,それは水族館につれて行かれてガラス越しに泳ぐサカナをみせられたのとたいして変わるものではない。前者が「実験」であって,後者がただの「見学」にすぎないというのなら,そこでの違いは器具の有無にすぎない。(中略)
「実験」が文字通りに「実験」でありうるためには,先の二つの命題のいう「たくましい想像・議論」が先行しなければならないのである。「仮説」を持って現象を観察・観測することが必要なのである。(科学と仮説,67p)
■科学がわれわれに与えてくれる自然像,自然観とは,今までのところ,そのような像として自然を描き,そのように観ることが有効であることが多くの実践・実験の結果によって確かめられてきたところの,一大先入観なのだと,私は考えるのである。(自然探検の仮説としての自然観,69p)
■ブルーナーの「どの教科でも,知的性格をそのままにたもって,発達のどの段階の子どもにも効果的に教えることができる」という「大胆で,しかも本質的な仮説」は,今や有名である。(同上)
■学習の途上で,子どもたちが種々に脱線したり,つまずいたりした場合に,どうすればよいかを教師があらかじめ考えないうちは,「教材」はまだ,それを構成しようとする当の教師において,つくられてはいない。「内容」と「方法」がばらばらの状態なのだ,といってもよいだろう。「教材」はだから,脱線・つまずきへの対策も含めて,当該の子どもたちの学習の可能性が,教師によってあらかじめ予想されているところの,選択され,配列された「ルール」-「(事)例」の集まりなのであろう。(科学の知識と土着の知識,87p)
Ⅳ章 科学的思考の心理学(大村彰道)
■一つの概念を学習するには二つの過程がある。一つの概念を他から区別する弁別(discrimination)の過程と概念を他の事例にも適用する(generajization)の過程である。この二つの過程を通してはじめて概念を使いこなすことができるのであって,単に「哺乳動物」という名や「母乳で育つ動物を哺乳動物という」といった定義を機械的に暗記しただけでは十分でない。(概念の学習,105p)
Ⅴ章 理科の教授法(平林浩)
■カリキュラム編成に当たって,教科の教育目的が明確になされなくてはならない。理科教育の目的はまず「科学を全ての国民のものにする」ために行なわれるべきものである。そして,さらに次のような人間の育成のために行なわれるべきものである。
① 民主的人間の育成
② 科学的方法を身につけ,科学的自然観をもつ人間の育成
③ 主体的に自分自身の考えをもって自然に問いかけ,働きかけることのできる人間の育成。
(カリキュラム編成はいかにあるべきか,145p)
■自然をありのままにみるとか,事象を関係的,分析的にみるというだけでは,自然の構造や本質の解明ができるものではないことは,すでに人類の科学の歴史が証明している。自然の事象をよく見るだけでなく,人間が自分自身の考え,すなわち,予想・仮説をもって自然に問いかけ,そこから答えを引き出して幾姿勢があったからこそ,目に見えない,体で感じられない自然の本質の解明へと近づいていくことができたのである。(自分自身の考えをもって自然に積極的に問いかける姿勢の育成,162p)
■自然認識能力の育成のためには,このような正しい意味での実験・観察の力をつけることが必要であり,その実験・観察に伴う技能は,それ自体が目的ではなく,必要から要求されるものなのである。技能が不十分なため,実験が正しい結果を生まないこともあり得るからである。(同上,166p)
■自然認識能力の育成は,以上述べてきたように,単に知的な能力だけではなく,人間の姿勢・精神作用まで含め,さらにその人間のもつ自然観まで含めて考えられなくてはならないものであろう。その意味で,理科教育が,単に何を教えるかという教材の内容からだけ問題にされていたのではいけないのである。(同上,168p)
Ⅵ章 実践記録の検討(礒田一雄)
■子どもの既成概念が自然法則の認識の自然法則の認識の正常な発展を阻害するときには,強烈な印象づけを行なうことによって既成概念をこわし新し概念を形成させる-これを『衝撃実験』と名づけている-のである。(「科教協」の「実践記録」-半沢健の場合,176p)
■全く同一の問題の難易度が授業の構成によって全く変わってくることがある,という事実にむしろ注目すべきであろう。学習すべき法則がある程度定着したかにみえる段階で,かえって逆に学習のつまずきが起こることがあるのであり,ここにも複雑な決定因子を含む授業という課程を実践的に研究する上でのむずかしさをみることができる。(「仮説実験授業」と「熊沢=板倉論争」,185p)
■引用図書
波多野完治・道家達将編著『教科の論理と心理5 理科編』(明治図書,1968年)
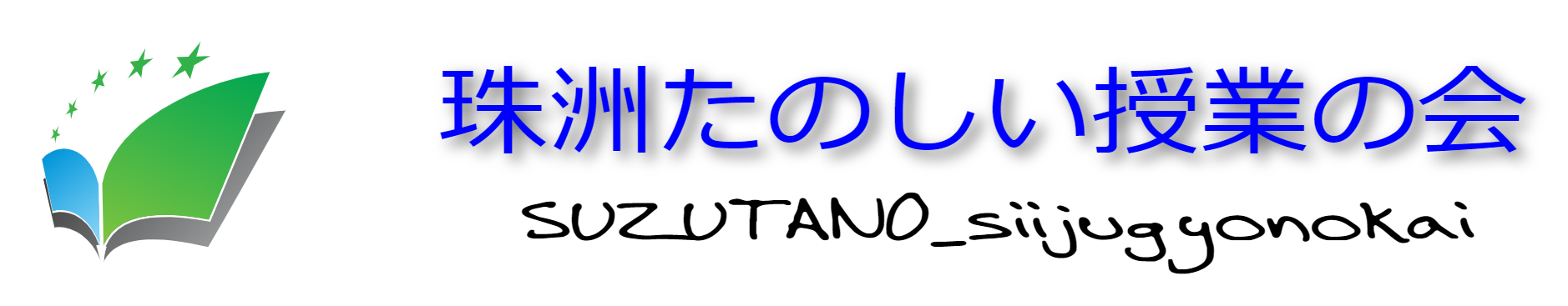



コメント