別ページ「都々逸を楽しむ」で紹介した都々逸は,主に中村風迅洞著『どどいつ万葉集』(徳間書店)からの引用でした。
本ページでは,都々逸に関する本の紹介と,その本に収録された都々逸から,わたしのお気に入りの都々逸をいくつか紹介します。
都々逸関連本も紹介しておきます。
都々逸に関する本(含:お気に入り都々逸)
杉原残華著『都々逸読本』(芳賀書店,1967,240ぺ,340円)
著者の杉原残華は,都々逸作家です。この本は,都々逸の入門書として,前半の六分の一くらいを「都々逸の生い立ち」にあて,後半の部分は「どどいつ名吟集」として,新旧織り交ぜてさまざまな都々逸を紹介しています。
この本のさし絵が,ちょっと粋です。「カラー版」なんて表紙に書いてありますが,さし絵にちょちょっと紅をさしたような感じなのです。これで「カラー版」とは笑わせるねえ。でも,本文とは関係なく挿入したという「さし絵」は,なかなかいい味だしています。ネットの古本やさんから手に入れました。
・わたしの人では ないひとなれど よそのひとにも したくない (平山廬江)
・三千世界の 烏を殺し 主と朝寝が してみたい
・もちつもたれつ 相合傘に よける浮世の 雨と風
・出来たようだと 心で察し 尻に手をやる 燗徳利
・花も紅葉も 散りてののちに 松のみさおが よく知れる
・文明開化で 規則がかわる 変わらないのは 恋のみち
・油高いと 早寝をしたら 米が高いに 子が出来た
玉川スミ著『ドドイツ万華鏡』(くまざさ出版社,1999)
ドドイツの本は,本当に少ないです。同人誌でもなかなか手に入りません。
それでこの本を見つけたときには,本当にうれしかったです。著者は,将にドドイツを歌ってきた人です。物心ついたころから都々逸の中で育ち,なんと3歳の時に初舞台を踏んでいます。ただ者ではありません。もうすぐ芸能生活80周年(本書出版時)を迎えるそうです。もう,すごいです。この本を読んでいると,三味線にのせた本当の都々逸を聞きたくなってきます。
・急げとばかりタクシー乗れば 時間はかかる高くつく
・逢うて嬉しき 笑いの種が 朝はなみだの 種となる
・よその夢見る 浮気な主に 貸して悔しい 膝枕
・逢いし苦労を するよりいっそ 逢わぬ昔が ましであろ
・壁に耳あり 徳利に口よ ちょくと話も 出来はせぬ
・君の便りを ただ松の月 憎や時雨のちぎれ雲
・山を通れば 茨がとめる 茨放しやれ 日が暮れる
・何度逢うても きらいはきらい 一度逢うても 好きは好き
・思い思われ 思われ思い 思う月日で また思う
・初めて見染めて 初めて惚れて 初めてはじめるはづかしさ
・人目くらます 手品の箱も 主にゃまことの 種明かし
・互いの心が 合い鍵ゆえに 胸の底まで あけた鍵
・主の広げた 大風呂敷に いつかこの身は 包まれる
・抜いてあげたい お前の口に 女殺しの 舌がある
・金が物言う この世の中に 目と目で物言う 恋の仲
・飲めば飲むほど やる気がわいて やった気になり 高いびき
・ビール1本 居座り続く コップの中の 人生論
・テメエコノヤロ もう辞めてやる 部長に言えず 独り言
・逃げる泥棒 子供を前に 赤信号で 立ち止まる
・おためごかしに 持ち上げられて 独立したら 孤立した
・墓のセールス いらぬといえば お若いですねと ひねくられ
・嫌な奴にも 笑顔でかわし 杯を重ねる かくし芸
・電話のベルに 思わず怯む 取ってはならぬ 第六巻
追伸:玉川スミさんは,2015年に亡くなられたそうです。享年92歳。合掌。
山本かほる編『新選都々逸佳集』(春江堂,昭和5年,30銭)より
◇四季とりどり
・末で添ふのを 妾(わ)しゃ松と竹 心一つを しめ飾り
・梅の匂いが あいにく洩れて 今朝は小鳥が 告げに出る
・心知り合ふ 互の中は 云えど跡なき 春の雪
・のぼる朝日の なさけをうけて 笑ひそめたる 梅のはな
・浮気鶯 梅をば棄てゝ 独り歩きの桃の花
・承知してする 苦労はうれし 雪の中にも笑ふ梅
・罪な人だよ あの花売りは 色でお客を 迷はせる
・はでな桜の 紅よりも じみな緑の松がよい
・花に蝶では 妾(わた)しゃ気がもめる 来てはちらちら迷はせる
・色も香(におい)もある 情けの梅に 糸を結びし 懸想文
・すねて見せても 程よい松は 藤が下から まとひつく
・泥にそまずに 一雨毎に 濡れて色増す あやめ草
・心真実 うつつになって 我が身 こがせる 夏の虫
・朝顔の 花のようなるお前の心 日毎日毎に 気が変わる
・待った甲斐なき 今宵の雨で 内に居ながら 袖ぬらす
・顔にほんのり 紅葉をのせて 秋の松葉のしをらしさ
・月はやさしく寝床にさすが 遅いお前の面にくさ
・すねて見せたり 跳ね返したり 知らぬ顔する 竹の雪
・越路の雪ほど あひびき積る とかす朝日は 主の顔
・雪にや止めたし 帰さに悪い 心二の字の 下駄の痕(あと)
・辛い別れの 朝風寒い 柳から降る 二度の雨
織田道代作・スズキコージ絵『ねこのどどいつあいうえお』(のら書店,2005年)
「都々逸でねこを読み込んだ言葉遊び絵本」ですね。これはたいしたものです。
右ページには創作都々逸が書かれていて,左ページには猫の絵が右ページはみ出すくらいに描かれています。その2つのコラボがたのしい本です。
ここに出てくる都々逸とねこは,ちゃんと「あいうえお」の50音順になっています。たとえば,「あ」と「い」を紹介してみると,
○あっちへいったり こっちにきたり とんだりはねたり あそぶねこ
○いつのまにやら すがたがみえぬ どこにいったか いないねこ
というような調子です。これで「ん」までいくんですから大した創作力ですね。
・おまけのいのち かるくまとって いねむりしている おいたねこ
・くらやみのなか けはいもけして めだけひからす くろいねこ
・しなやかなあし しずかにはこび ふりむきもせず しゃれたねこ
・ずずめおいかけ にげられちゃって そしらぬふうの すましねこ
・つめをといでは やみをきりとる こよいのつきを つくるねこ
・ともだちだよね そうおもうのに よんでもこない とんだねこ
・ぬすみじょずな まあるいあしで またもこころを ぬすむねこ
・みみだけきゅっと こちらにむけて きいていながら みないねこ
・ゆっくりいきして ひげふるわせて とじためでみる ゆめのねこ
・レースのカーテン みればとびつき よーいどんする レースねこ
遊泳舎編・いとうあつき絵『26文字のラブレター』(遊泳舎,2019)
これまでに出版された本から,編者お気に入りの都々逸60章(歌?句?)を集めた本。
見開きに都々逸1章と,その句の簡単な解説(編者の思い)ときれいな絵がセットになって表現されています。特に,あわい色の水彩画がこの本の雰囲気の全てといっていいかもしれません。
都々逸そのものをたくさん読みたかったら,他の本をあたった方がいいと思います。3分の2以上はわたしが知っている都々逸でしたから。
本書は,喫茶店か美容院にでも置いておいて,パラパラと味わう本だと思います。
末は袂を絞ると知れど 濡れて見たさの夏の雨
これを作ったのは陸奥宗光らしい。知らんかったなあ。
・胸で苦しき火は焚くけれど煙立たねば人知らぬ
・切れる心はさらさらないに 切れたふりする身のつらさ
・染めてくやしき江戸むらさきを 元の白地にしてほしい
・殿は雨夜の月影なるか 心も知らぬ行末を
・痴話はいつしか洋灯(ランプ)とともに 消えて時計の音ばかり
・雌蝶雄蝶の杯よりも 好いた同士の茶わん酒
・人の口には戸を立てながら 門を細めにあけて待つ
・お前死んでも寺へはやらぬ 焼いて粉にして酒で飲む
吉住義之助監修・小野桂之介著『都々逸っていいなあ』(角川書店,2021)
調子に乗って久しぶりに購入した都々逸本。本書は,古典都々逸ではなく,現代都々逸作品を集めています。
わたしは,どちらかというと色恋ものが好きなのですが,サラリーマン川柳やシルバー川柳のような内容の都々逸も,面白いとは思います(ただ,こういう内容ならば川柳に任せておけよ…とも思う)。現代都々逸作品で,わたしが「お,気に入った」と思うものは,やっぱり男女のものだったりしますから。現代都々逸を自分で作り始めたりすれば,そのよさも分かってくるかも知れません。
本書にも載っていますが,都々逸を自作するときのきまりのようなものを紹介しておきます。
「都々逸の作り方」指南
都々逸は7775のリズムですが,さらに,34,43,34,5のリズムで作るのが一般的です(正調といいます)。これは,もともと都々逸というものが音曲に合わせて歌うことから来ているリズムらしいです。
たとえば,美空ひばりの「車屋さん」に出てくる都々逸を聞いてみると,
♪歌の文句にあるじゃないか~
○ひとの こいじを じゃまする やつは まどの つきさえ にくらしい
○あてに ならない おひとは ばかよ あてに するひと もっとばか
という工合になります。
YouTubeで聞いてみてね~。
・勝手口から女房と犬が 出掛けて静かな午後となる 秋霖
・両手ひろげて虹ひとり占め 好きと言われた雨上がり 弓
・夕陽に染まった海穏やかに ふたりを二人っきりにする 秋霖
・綾とりしているよな路線図を 縫ってあなたに逢いにいく 智華
・ママのお腹に耳押し当てて 二歳がゆっくり兄となる みや
・はな丸貰った子の作文の 中に我が家が素っ裸 野出
・たまに下宿に顔出す母が いっぱい詰めてく冷蔵庫 絵日傘
・覚悟はしてたが娘の部屋に 寂しく鳴いてる鳩時計 ときを
・座右の銘など俺にはないが 親の叱言(こごと)の山がある 義之助
・見つからないよに見つかるように 孫と爺じのかくれんぼ 弓
・文化国家は天然水を ペットボトルで買って呑む 安次郎
・粋と云う字は米寿に卒寿 粋に生きてりゃ吉が来る 俊男
都々逸に関する本
吉川潮著『浮かれ三亀松』(新潮社,2000,370ぺ,1800円)
柳家三亀松って,ご存じですか? 大正末から戦後まで一世を風靡した(らしい)天才芸人です。主に都々逸を唄って,それに声帯模写なども取り入れていたそうです。
この本は,その三亀松の「一代記」と言えます。いろいろな資料から,その波瀾万丈な人生が綴られていて「伝記」として,面白く読みました。
で,読んでいるうちに三亀松の声と都々逸の歌い方が聞きたくなりました。当時は,結構レコードにもなり,それなりに売れたそうなので,「どっかにSP盤でもないかなあ」なんて思っていたら,ちゃんとCDになっている事を知り,手に入れました。
右のリンクは文庫本です。
『コロンビア邦楽 都々逸 柳家三亀松』(COCF-11666)
『風流いろくらべ いろ笑粋談 柳家三亀松』(KICH-3189)
2023年9月現在のAmazonでは,他にもいろいろなCDが手に入るようです。
川崎勝平著『舞鶴叢書・都々一坊扇歌』(常陸太田市,1989)
都々逸に凝って早5年?(注:西暦2000年のことです)。 この方面の本はなかなかありません。古本にもないのですが,やっと1冊見つけました。
本書は,都々一坊扇歌の生まれ故郷である常陸太田市が出しています。小さな冊子ですが,なかなかのお値段です。市のホームページでこの本のことを知り,注文しました。
右の画像はリンクされていません。あしからず。
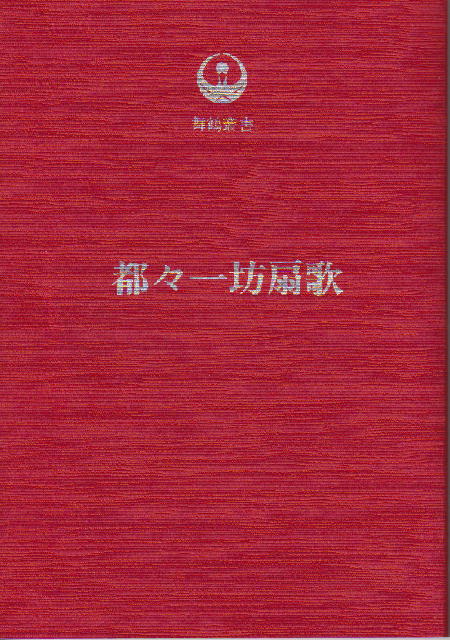
中村風迅洞著『風迅洞私選 どどいつ万葉集』(徳間書店,1992)
古典都々逸に3分の1,現代どどいつに3分の2,合計2000句あまりの「どどいつ」が紹介されています。わたしが一番最初に手に入れた都々逸本です。
中村風迅洞さんとは,なんと電話でも会話しました。それは,ある限定本を手に入れる時に確認を取ったんです。風迅洞さんから連絡が来ました。
現代都々逸を盛り上げてくれたのが風迅洞さんです。
「都々逸を楽しむ」に紹介した作品と共に,まず,味わって欲しい著書です。
中道風迅洞著『二十六字詩・どどいつ入門』(徳間書店,1986)
こちらの著作は,「どどいつ」の生誕から,江戸,明治,大正,昭和と,都々逸がたどってきた道筋をわかりやすくまとめています。「文明開化都々逸」や「翻訳された都々逸」なんて初めてみました。
都々逸は,楽しいよなあ。
自分でつくるなら折り込み都々逸からどうぞ…とも言っています。アクロスティックの遊びから,都々逸に入門するってのもおもしろそうですね(アクロスティック[折句]という言葉もちゃんとこの本に出てきます)。

内館牧子著『小粋な失恋』(講談社文庫,2000)
古典都々逸から,著者が50首ばかり選りすぐり,その都々逸を解説しながら現代の「男と女の心の機微」についてエッセイを書いています。著者は,NHKの朝の連続小説「ひらり」の脚本家であり,『義務と演技』の著者であることをしりました。
「どどいつ」について,「ちょっとくだけた本から読んでみたいなあ」というかたにお薦めの本です。もともとは『With』という雑誌に連載したものを文庫本化したのですから,読みやすいのもわかります。
右のリンクは,Kindleの製品に飛びますので,そこから,単行本なり文庫本に移動してください。
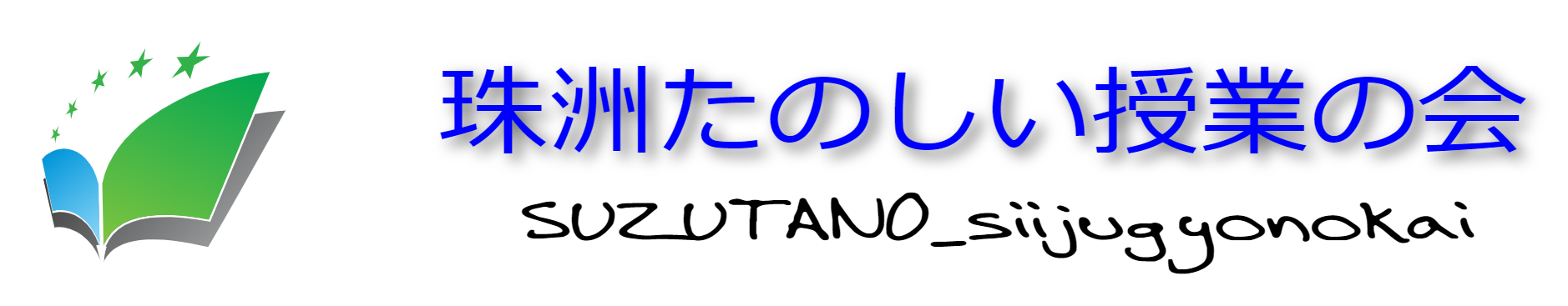
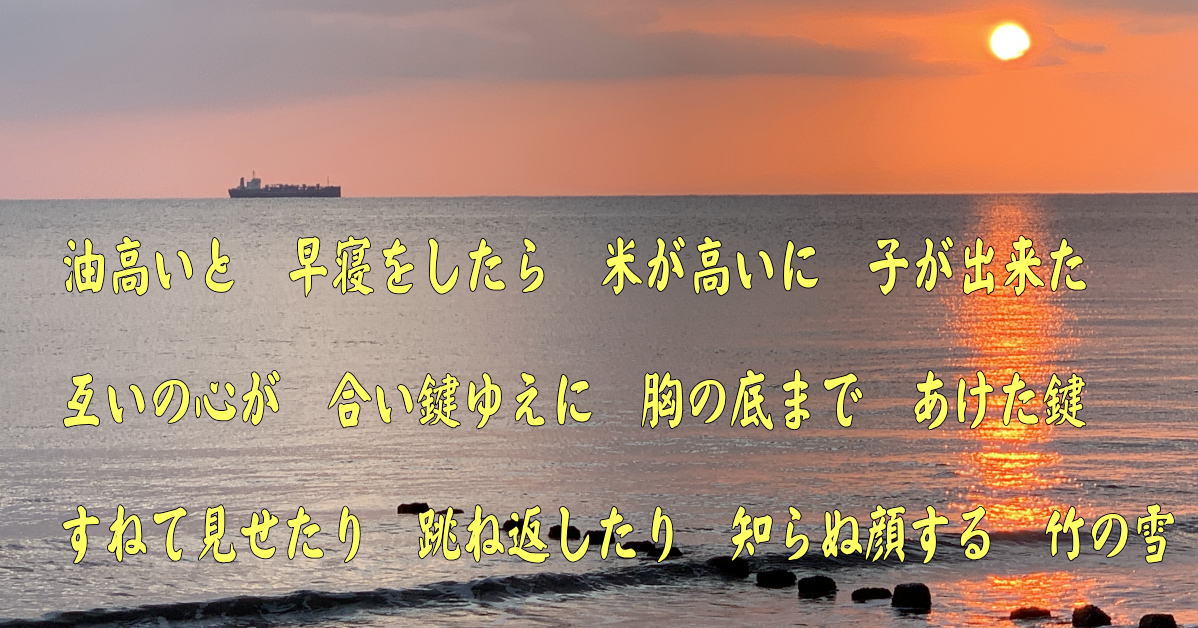










コメント