はじめに(2016年12月のレポートより)
2016年度の金大附属小の発表会の折,附属の学校長が,一日目だったか,二日目だったかの最後のあいさつで,ワロンという心理学者を取りあげて話をしていました。あいさつ自体が短いので,ワロンについてもたったの一言触れただけでしたが,ピアジェとの対比で話された言葉が,妙にアタマにこびりついてはなれませんでした。
「これまでの教育は,一人一人の認識の問題ばかりに目がいっていたけれども,人は関わりの中で育つことをもっと大切にすることが必要ではないか。昨今,ピアジェと同時代に生きたワロンの考え方が見直されてきているのも,そういう流れがあるからだろう」
というようなお話だったと記憶しています。
仮説実験授業も知識構成型ジグソー法も,子どもが一人で授業するようなものではありません。科学的な認識がどのようにして個人の概念として確立されていくのか…ということにつていは,確かにピアジェの研究に寄って立つことはたくさんあるでしょう。しかし,たとえば,仮説実験授業においては,そもそもの理論的な構えとして「科学的な認識は社会的な認識である」という視点まで入っています。けっして,個人だけで科学的認識が成り立っているという話ではないのです。
先の奥能登学教研での授業のふり返りでも,私は,教師の指導法よりも,学級の子どもたちを授業にどう関わらせるのかの方に重点をおきたいなと思う気持ちが強くなっていることを話しましたが,それもワロンと大いに関係あるのです。そんなわけで,ここ1か月,ワロンに関する本を手に入れて読んでみることにしました。
附属の発表会が11月19,20日。帰宅後,すぐに,県立図書館の蔵書からワロンに関する本を探してみました。4冊見つけました。それをすぐに予約。11月25日(金)には,学校に来て下さっている図書館司書を通して私の手元に届きました。それと並行して,アマゾンで,ワロンに関する最新刊の本(2015年10月発行)を注文。まずは,こちらの方から読んでみました。
本の紹介をする前に,まず,Wikipediaで「アンリ・ワロン」の項目を見てみましょう。
アンリ・ワロン(Henri Wallon, 1879年 – 1962年)はフランスの精神科医、発達心理学者、教育者。
Wikipedia
フランス・パリ生まれ。1937年から1949年までコレージュ・ド・フランス教授を務め、国立科学研究センターで研究を行なった。1948年にはパリ大学の心理学研究所の所長となった。アンリ・ワロンは、人間の成長・発達(個の歴史)を歴史(共同の歴史)とともに全体としてとらえようとし、ヨーロッパで500年以上積み重ねられてきたあらゆる哲学・心理学、そして精神医学を吸収しようとした。
たったのこれだけです。ビックリですね。
それでは,以下,すでにブログで紹介した文章を,一部手を入れながら転載します。
本HP上では,さらにその後の本も紹介しておきます。
ワロンを学ぶ
加藤義信著『アンリ・ワロン その生涯と発達思想』(福村出版,2015)
アンリ・ワロンのことが知りたくて,先ず手にした1冊目の本です。
最近,ワロンの思想が見直されていると聞いて,興味を持って読み始めました。
ピアジェと同時代を生き,同じ心理学畑で研究をしながら,〈日本の教育現場への影響〉という観点でいうと,これまでは圧倒的にピアジェに軍配が上がっています。わたしの職場のみなさんも,老若男女問わず,ピアジェなら知らない人はいないでしょう。
さて,そのワロン。当時,フランス共産党にも関係があった関係で,アメリカあたりでは学問の成果云々の以前に門前払いを食っていた感じもあったようです。まあ,東西冷戦という時代ですから,やむを得ないですね。共産党を文字通りの色眼鏡で見ていた時代ですから(今でも,共産党と言うだけで毛嫌いする人たちが日本にもいますが…まるで思考停止です)。
本書を読んで,ワロンの生い立ちや,ワロンが研究しようとしていた「全体としての子どもの姿を捉えたい」という姿勢くらいはなんとか分かりましたが,いざ,ワロンの発達論の話になると,分かりづらかったです。
第3章「アンリ・ワロンの発達論はなぜ難解か?」という章まで設けるほどのワロンの論理ですから,一読したくらいで分からないのは,仕方ないのかな。
著者は,初期の頃の訳書はわかりにくい…と言っています。是非,分かりやすい訳本を出してほしいです。
今,続けて,他のワロン関係の本もかじっていますが,そこでも,ワロンの論理の難解さと,訳本の稚拙さが指摘されていて,ワロンの論理を日本語で理解するのはなかなか難解なようです。
だれか,分かりやすく教えてくれないかなあ。
ワロン著/浜田寿美男訳『身体・自我・社会:子どものうけとる世界と子どもの働きかける世界』(ミネルヴァ書房,1983)
ワロンに関する本を読むのは,これが2冊目。いよいよワロンにハマってきています。
訳者は,「はじめに」や「あとがき」でワロンの文章はとても難解だといいます。しかも,以前に日本語に翻訳されている著作はとても読めたものではないものだと,次のように述べています。
▼ワロンの理論自体の難解さはともかくとしても,アカデミズムにしか通用しない,いやもっと言えば,本来通用するはずのないものでもアカデミズムでならば通用する,そういうけったいな風潮にのっかっているようなことろがあるとすれば,それは許されるものではありません。
こういうことをいうと,それは全て訳者自身に跳ね返ってくることであることも自覚しています。
本書は,章ごとに「ワロン論文の訳文と訳者の解説」というペアでまとめられています。ワロンに限らず,こういう論文というのは,専門用語がちりばめられていて,スムーズに読めるものではありません。それは,ピアジェの論文だって同じことです。それで,訳者の解説がとても役に立ちます。
ワロンの全体像は,まだまだ私には理解できませんが,ワロンが寄って立とうとした研究の視点と子どもの捉え方は,ピアジェとの対比の中で,だんだんと分かってきました。
▼ピアジェとの対比において見るとき,全体性をそのさまざまな矛盾を含んだ姿のまま,多面性を多面性のままとらえようとするワロンの全体的志向が,鮮やかに浮かびあがってきます。彼の方法が弁証法的だと言われるゆえんは,おそらくここにあるのです。(267p)
弁証法的な思考で人間を捉える,なかなか興味深い話です。
1冊目の本にも,「ワロンの考え方は弁証法的である」という紹介がありました。個人というものを確立された純粋なものと見るのではなく,歴史的な存在として見るとか,依存しながら自立しているとか,とにかく,弁証法的な発想がそこかしこに出てくるような気がします。
私は,物事を見るときに多面的に見る(あるときは多面的に見ない)…こういうことが弁証法的だと思っているのですが,そういう部分がワロンにはあるようです。ますます面白くなってきました。(2016.12.09読了)
浜田寿美男著『ピアジェとワロン―個的発想と類的発想』(ミネルヴァ書房,1994)
第1部がピアジェが描いた世界(批判的再検討を含む),第2部がワロンが描いた世界(ピアジェと比較しながら),そして第3部は,発達心理学者としての2人の理論の違いがどこにあり,それはどうして生まれたのか,2人の理論の現代的な意義は何かなどについて,筆者の考えが描かれています。
ピアジェについては知っていたつもりでしたが,よく考えてみれば,ピアジェの著書そのものをしっかり読んだこともないことに気づきました。ただ,なぜか,ピアジェの発達理論や科学的な認識に至るまでの段階論は,知っているつもりになっています。これは,これまでも算数科や理科の理論本,さらには児童心理学関連の本を読んできたからだと思います。
一方,ワロンのことは,1か月前までは名前くらいしか聞いたことがなく,ピアジェと同時代を生きていたことさえも知りませんでした。
個人の認識を単なる個人の中のこととして取り扱うのか,それとも,社会的なつながりの中で取り扱うのか,そんな違いが,ピアジェとワロンにあるのではないかというのが,2人の違いに対する,最も簡単な私の捉え方です。
▼「純粋状態における子ども」とか「純粋な能力」などというものはない,あるのはつねに状況の中の子ども,時代の中の子どもであり,なんらかの対象に関わって用いられる能力なのである。これが,ワロンの発達論の大前提である。(本書140ペ)
いくら,個人が,個人内部で科学的な認識を得たとしても,それを彼がどのように現実世界に結びつけながら,どの方向に向けて活かしていくのかは,まわりの環境に大いに左右されるはずです。そもそも,その認識を得るまでにも,どのような環境に育ってきたのかが大きく影響を受けるのも言うまでもないことでしょう。以前,ジーン・レイヴ他著『状況に埋め込まれた学習』(佐伯胖訳,産業図書)を読んだことも思い出しました。
▼「できないときどうするか」という,私たちにとってごくごく日常的な問いに対して,ピアジェ的枠組みを代表する今日の発達心理学においては,単に「できるようにする」というトートロジカルな答えでしか応じられない。しかし,これはまことに奇妙なことではないか。そこに現代社会特有のイデオロギーを看取してもあながち不当とは言えないように思える。つまり,冒頭に触れた〈個体能力論的イデオロギー〉がこういうところに如実にあらわれていると言ってよい。(184ページ)
ワロンの「姿勢・情動論」は,上記の疑問に真摯に向き合ってくれそうです。(2016.12.13読了)
そうこうするうちに,Nさん(珠洲たのメンバーで金大附属小勤務)から,校長先生が参考にしている「ワロンの本」の情報を得ました。
まず一冊は,私が紹介した浜田寿美男さんの上の本。もう一つは,波多野完治監訳の『ワロン選集』(上・下,1983年発行)です。波多野さんたちの訳本は,もうしばらくしたら購入しようと思います(この欄の最後にリンクだけ付けておきます)。
次に私が読み出したのが,ワロンの2冊の著者である浜田寿美男氏の本です。難解だと言われるワロンの理論を追うことはここでいったん打ち切って,ワロンを紹介してくれている浜田氏が,ワロンの理論を自分の心理学や学問にどのように適用しているのかが,気になったのです。そこで,今度は,アマゾンの古本を注文しまくりました。
ワロンの著作
ワロンから学ぶ…浜田寿美男さんの本
以下は,ワロンの研究者であり発達心理学者の浜田寿美男氏の著作を紹介したい。彼の著作のおかげで,子どもを集団の中で見ることが意識してできるようになったと思う。浜田氏の本を読んだあとで,ワロンの著作にあたるのもいいだろう。
『〈子どもという自然〉と出会う――この時代と発達をめぐる折々の記』(ミネルヴァ書房,2015)
ワロンの本を探している中で出会った研究者です。出会ったと言っても本の世界でのことです。
本書は,著者が子ども情報研究センターの月刊『はらっぱ』に連載してきた文章を再編集したものです。期間は2007年~2012年まで隔月です。
「子どもの世界,おとなの世界」と題されたその連載の話題には,冤罪事件にからんだ話がたくさん出てきます。一瞬,これまでのワロンの話とつながらなくて「なんでだろう」と思ったのですが,読み進めていくうちに,合点がいくようになってきました。
一般に冤罪を生む原因の一つに「自白」があります。冤罪のときには,明らかに,本人はやっていないわけで,自白できるはずはありません。なのに,なぜ人は「自白」してしまうのか? 「それは,取調官に自白を強要されたからだ…」で終われない〈被疑者が置かれている現状があるからだ〉と著者は言います。
犯罪者にしたてられ,世間だけではなく身内とも隔離されて1人になった人は,これまで当然あった〈世界とのつながり〉が切断されてしまいます。人が,世界とのつながりが切れるという恐怖に耐えることはともてむずかしいのです。そんな状況に置かれている時に,うその自白であっても,それを話すことで,目の前にいる取調官が優しく接してくれるようになる。もう一度世界とのつながりが感じられるようになるのです。こういった人間の心理の中で,自白は作られていくのです。
著者は「強いられた自発性」といった言葉も示してくれます。
今の学校は,まさに「強いられた自発性」を要求されているのではないか。学校で,自分の本当の気持ちを押し殺しながら〈積極的に生きているよう〉に見せる子どもたちの姿は,世界とつながりたいがためにわらを藻つかむ気持ちでうその自白を話し出す被疑者の姿とオーバーラップして見えてきます。
発達心理学の研究者であるにもかかわらず,「発達」という言葉に違和感を示す著者。
「今の流れが〈錯覚の流れ〉だということに気づいて,自分だけ走るのをやめたら,いつの間にか少数派になっていた」とも。
少数派は少数派として,堂々と,そして,結論を急がず,子どもたちの現状を見ながら生きていきたい…そう思いました。
まさに「優等生になることを拒否しつつ,自信を持って生きる」ことが大切ですね(本書にはこんな言葉はありません)。
大人たちは,もっともっとしっかり学ばねばならない…と思いました。
大人たちには,流れの中で立ち止まったり,流れから外れたりできなくても,せめて,〈錯覚の流れ〉の中にいることだけでも,気づいていて欲しい…。(2016.12.14読了)
『子どもが巣立つということ―この時代の難しさのなかで』(ジャパンマシニスト社,2012)
「発達」心理学者の著者が,現在の子どもの置かれている状況を深く見つめた内容の本です。
今,子どもの生活の場である学校や家庭は,子どもが巣立っていく(社会に出て行く)ために,何か準備をできているのでしょうか。
人が「巣立つ」とき,それは,完全な独り立ちを意味するわけではありません。一個人としての自立を意味するわけでもありません。著者の言葉を借りていえば,
「巣立つということは成熟するということではないこと。形容矛盾を覚悟していえば,人は未熟のまま,しかし巣立つ。そういうものかもしれません。」(本書240ページ)
「飛ぶ準備がととのって,安心して飛び出すというものではなくて,むしろ時が来て未熟なままに飛び出す。そして,飛び出すことによって,飛べるようになる。逆説的なようですが,それが実際です。」(245ページ)
巣立つというのは,これまでの,親を中心とした人間関係の網の目からはなれて,自分を新しい人間関係の中に入り込ませることでもあります。そのとき,すでに親以外の人間とのつながりを持っているかいないかで,その巣立ちが成功するかどうかに大きな影響を及ぼす可能性もあります。
さらに,未熟な人間が巣立つためには,当然,後押しがいるでしょう。巣立った後のサポートも必要でしょう。これらもまた,自分が社会と関わっていく中にあるし,それに支えられて生きていくのでしょう。(経済的に,あるいは精神的に)親元を離れたとき,新しく広がる社会の中にも,後押しやサポートがあると感じることができれば,彼,彼女らは,石橋をたたいて堂々と渡っていくことができるような気がします。
自分一人で生きていくことはできない。「巣立ち」という自立の現場を切り取ってみただけでも,そこには,沢山の人とのネットワークとその影響があるわけです。
「自立は,孤立ではありません。とすれば,子どもたちの自立を考えるうえで問題となるのは,自分の力で生きるという時の,その力をどう高めるかという以上に,むしろ子どもたちを囲む関係の網の目をどう作っていくかにあるのではないでしょうか。」(40ページ)
「子どもに学力つける」といって,学力調査の点数をあげることに血眼になっている学校現場に,以上のような発想はまったくありません。
生きてはたらく力にさえなっていない「学力」の向上を目指すことをやめ,友だちと,あるいは先生と共に生きている楽しさに気づく学校。そんな学校ができればいいな。少なくとも,子どもが疎外感をもち,自信をなくしていくような学校現場にはしたくありません。
本書には,犯罪を犯してしまった若者の実例(著者が相談に関わっている)が出てきますが,その事件の原因を,加害者になった若者の個人的な資質に求めることの危険性もよく分かります。
これまで,自分たちの社会の〈内〉にいたはずの少女や青年を,犯罪を犯した途端に〈外〉に追いやり,そして,犯罪を起こした原因をその子の精神状態や障害のせいにする。それは,同時に,自分たちの社会を〈外〉から守るために,〈内〉に新たな障害者差別の意識を広げることにもなりかねません。彼女らが,犯罪を犯すまでは「自分たちの〈内〉にいた」ことを思えば,その「自分たちの〈内〉の構造」こそ,見直すべきだと気づくはずなのです。
とても読みやすい本でした。そして,著者の主張もよく理解できました。(2016.12.17読了)
『「私」とは何か』 (講談社選書メチエ,1999)
「私」ができあがっていくためには,実の多くの環境要因が絡み合っていることは,当然と言えば当然です。発達心理学者である著者は,乳児~幼児の観察や,自閉症の子どもたち,障害を持った子どもたちの実例を通して,「私」がどのように形成されていくのかを分かりやすく説いてくれます。
他者と絡み合いながら,「私」ができてきます。しかし,その「できた」と思っている大人の「私」でさえ,他者なしでは,何もできません。自分の意志だけで,なんでもできると思っている人がいるとすれば,それは誤謬でしょう。
著者は,自らが名づけた「発達論的還元」という手法を駆使し,私たちが言葉というものを身につける過程を興味深く示してくれます。
最終章では,羞恥心について,その出所がどこにあるのかを教えてくれました。私たちは世間の中に生きているのですが,その世間には,「私」も含まれています。「私」も,得体の知れない世間をつくる部品の一つなわけです。だから,世間の目を気にしてわき起こる「私」の羞恥心は,実は,もう一人の自分がいるからこそ起きてくるものだということが分かります。その世間を力で変革することはむずかしい。しかし,自分もその世間の一部であるのなら,自分の行動を少し変えていくことで,世間も変化するのではないか…なるほど,そういう手があったか…と思いました。(2016.12.23読了)
『障害と子どもたちの生きるかたち』 (岩波現代文庫,2009)
大学のゼミに参加するようになった自閉症のたかし君と,学生として大学にきていた手にけがのあるみつこさんの話を中心として論は進んでいきます。この両者の話は,以前読んだ,同著者の『「私」とは何か』(講談社,1999年発行)にも取りあげられていますが,本書の方が二人の子どもの成長の過程が詳しく取りあげられていて,分かりやすいです(本書の元になった本は,1997年発行ですから,読む順が逆ですね)。
障害を文化と考えて付き合うことの可能性が,しっかり見えてきたような気がします。
本書を読み進めるうちに,昨今の特別支援教育の流れは,間違っているのではないかと思ってきました。ほんのわずかな障害でさえも「その子にあった教育をするため」という大義名分の下で分けられてしまい,障害のある子だけが,ない子に近づくように仕向けられているような気がします。
▼ほころびは,なにも訓練や治療によって彼の側から埋める必要はないのです。彼の生きるかたちのまま,私たちは自分たちの生きるかたちをそこに絡ませ,交歓の世界をつくりあげることができるのですから。(本書123ぺ)
本来なら,障害を持った子も持たない子も,同じ空間を共有しながら,どっちとも学んでいく。障害をもっている子たちとの交流を,異文化の交流として捉え直していくことで,障害者とともに歩む道が見つかるのだと思います。(2016.12.24読了)
『発達心理学再考のための序説―人間発達の全体像をどうとらえるか』(ミネルヴァ書房,1993)
著者が,季刊『発達』に連載してきた「発達心理学セミナー」のうちの最初の16回分(1986年-1990年)とその雑誌に掲載した論文を組み入れ編集された本です。このシリーズは,4冊の担当本として出版されています。私は4冊目を先に読んだのですが,最初から読みたくなって,1冊目から手に入れて読んでみたというわけです。著者はあとがきで「私にとって発達関係の単著としてこの本が最初のものになります」と書いてあるように,まずは,この本から読むのが,著者の研究の流れを知るうえで大切なようです。
わたしにとって浜田さんの本は,これで8冊目となります。これまでは,彼の研究の流れが今ひとつわかりにくかったのですが,このシリーズを読むことで,発達心理学への研究のこだわりなどが見えてきたような気がします。発達心理学の研究者でありながら,これまでの発達心理学が目指している方向に違和感を感じる著者。読みするめるうちに,その違和感がどこから来るのかが,少しずつ明らかにされてきます。
本書で,私は「できるとするは違う」という言葉に注目しました。
私たちは,とかく〈子どもたちができるようになること〉と目指して教育をしています。しかし,考えてみると,その子が〈できる能力〉を得たとしても,その能力を使う=〈する〉かどうかは,また,別の問題です。〈する〉ためには,その場の雰囲気や人との関係性が大切になってくるからです。
考えてみると,学校現場にいる者にとってば,これは当たり前の事です。とたえば,教室でも,よく「〈できる〉はずの生徒が,手あげて発表してくれない」と嘆く教師がいますが,それは,〈できる〉ことと〈する〉ことの違いから来ているわけです。なぜ,手を挙げて発表しないのかは,まわりの人間関係が大きくものをいうことが多いというのも,ほとんどの人が経験していることでしょう。
「できること=能力」として,これのみに重きを置いてきたのが,これまでの教育ではなかったでしょうか。まさに,点数をあげるという能力主義が跋扈してきたのが,日本の教育界だったのです。残念ながら,この状況は,今でもあまり変わっていません。
今後,アクティブ・ラーニングとかで,子どもたちが,がんばって〈意見表明できる〉ようになることをめざすようですが,そこでもやっぱり〈教室の中でできる〉ようになっても,それを〈日常生活でする〉かどうかは,全く分からないのです。
著者の一言,紹介します。
▼能力発達に絶大の期待を寄せる人々が世間にひしめくばかりで,その当の能力を用いて生活世界をどうふくらませ,豊にしていくのかを見ようとしない奇妙な現実がはびこっているのではないでしょうか。(本書236pより)
今,学校では〈過不足なく説明する力〉を求められています。が,本来,人間同士の会話の中では,説明不足だと思えば相手は問い返してくれます。そして,不足分を補って応える…そういう応答こそ,学ぶべきことではないでしょうか。私たちは,もっともっと,子どもたちが,人間関係の中でどのようにして生活を豊かにしていくのかを考えなくてはなりません。このことは,引き続き,ワロンの著書にあたりながら,考えていきたいと思います。(2017.02.01読了)
『意味から言葉へ―物語の生まれるまえに』(ミネルヴァ書房,1995)
本書は,『発達心理学再考のための序説』の続編であり,季刊『発達』に1990年~1995年まで連載した20回分の文章に加筆したものである。これ以降の連載も,あと2冊,単行本になっている。
さて,一般的に,人は,言語を獲得してのちに,それを使って他者とのコミュニケーションを取るようになると思われているが,それは本当だろうか?
考えてみると,赤ちゃんには,言語を獲得する前から,すでに,周囲の人とのやりとりの世界が存在している。母親からは,母国語でのいろんな呼びかけがあり,赤ちゃんの発する言葉(喃語のようなもの)に対しての反応もある。赤ちゃんは「周囲の人とのやりとりの世界を次第に膨らませ,相互に共有の意味世界を広げて行」くのであろう。だから,まだ言葉とは言えないような「単発的に発せられた語すら,その前後の行為のやりとりの文脈を考え合わせれば,それ自体がすでに対話の一コマなの」だと言えるのだ。
以上のことは,云われてみれば当たり前の事である。むしろ,言葉というのは,こういう対人関係があってこそ,育まれていくのであろう。
こういう当たり前のことを確認することこそ,現代の子どもの置かれている状況を見直すことができるのだと著者は云う。(2017.02.05読了)
『私と他者と語りの世界―精神の生態学へ向けて』(ミネルヴァ書房,2009)
感想は書かなかったので,Amazonの紹介文をコピーしておきます。そのうち,再読して書くかもしれません。
■障害をもつ子どもたちの生活世界論からはじまった浜田心理学ワールドは、個体能力論の枠組を超えて、物語の形成論にまでその射程を広げてきました。本書は、そこに人々の日常の対話、歌、そして冤罪事件の供述分析をも組み込むことで、人々がその渦中で生きる「主観」の世界を、精神の生態学として記述しようと苦闘しています。『発達』に22年間連載してきた「セミナー発達心理学」の最後をかざる単行本化。労作の完成。(2017.02.16読了)
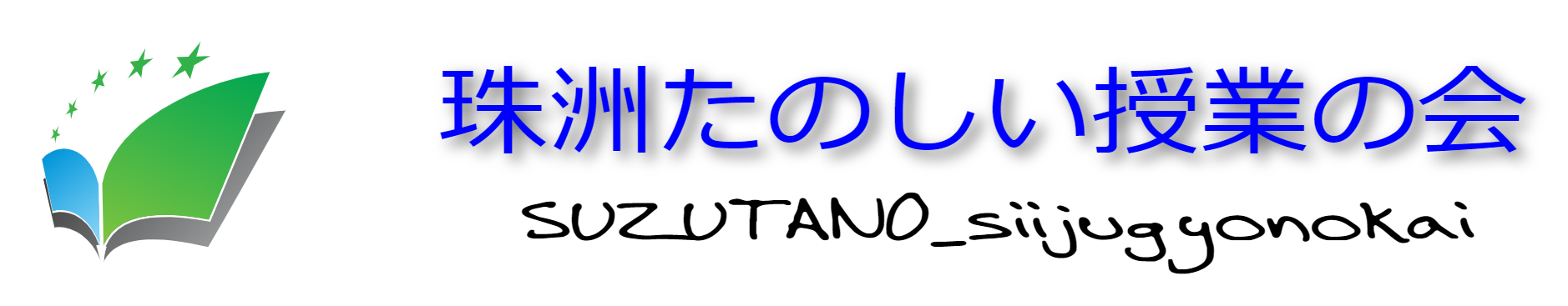
















コメント