珠洲市内で見つけた「昔から日本にいる植物(在来植物)」を紹介します。いずれの在来植物も,よく似た外来種よりも,なんとなく,背丈は小さく,花もちょっと小さくて可憐な雰囲気を醸し出しています。そう感じるのは日本人の欲目なのかな?
登録順は「花の咲く時期順」にしてあります。一般的に,花(やそれに似たもの)が咲いたり,実がなったりしないと,植物は注目されませんからね。特に花が咲いていると「この植物の名前を知りたいな」と思いますよね(少なくともわたしはそうです)。
ここでは,主に草類(こんな言葉があるのか知らないが)や低木類を紹介してあります。なお,解説文は主に,花検索アプリ「花しらべ」を参考にして書いてあります。
タチツボスミレ(立坪菫) スミレ科 花期:3月~5月
雪が解けて保全林に入ると,まず目に入ってくるのが,このタチツボスミレです。耐寒性の多年草なので,北陸でもしっかりと自己主張しています。
「名前の由来は,開花してしばらくすると茎が立ち上がり,坪(狭い庭のこと)などに生えることから」(花しらべ)ついたそうです。
花の色は,紫だけではなく,白や青っぽいのもあるそうです。葉っぱの形はハート型。まわりにはギザギザがあります。(三崎町,2023/03/25)


キクザキイチゲ(菊咲一華) キンポウゲ科 花期:3月~4月
春,アカガエルの調査をしようと,いつもの水田に出かけたら,近くの湿った林縁に,写真のような薄紫色の花が可憐に咲いていました。この種はスプリング・フェメラル(春植物)のひとつだそうです。名前の由来は読んで字の如く。菊に似た一輪の花をつけるから。花びらに見えるのは萼片。
花の色は,白・青・紫といろいろですが,日本海側では紫が多いらしいです。まさに,この写真の通り。(三崎町,2023/03/31)


シュンラン(春蘭) ラン科 花期:2月~4月
ランという名前がつくのだが,さすが在来種らしく,大変控えめな花です。普通に歩いていると,葉に紛れて花に気付かないほどです。慣れれば,「あ,ここにも,ここにも…」となりますけれどもね。
能登には「春蘭の里」という里山で宿泊体験ができる地域もあります。山林の半日陰に自生していて,なかなかステキです。別名をジジババ(爺婆)なんて呼ぶこともあるそうです。「花しらべ」には,「花びらの様子を,腰の曲がったおじいさん,おばあさんに例えて」と書かれていましたが,知り合いの先輩は,ランの中のおしべ・めしべの話をしていました。(三崎町,2023/04/01)


イカリソウ(碇草) メギ科 花期:3月~6月
花はとても特徴的なので,一度見たら忘れられないと思います。近所の林縁に咲いていました。名前の由来は,花の様子をイカリに見立てたもの。別名「三枝九葉草」とも呼ばれるそうです。3本の柄に3枚ずつ葉がつくからだそうです。3✕3=9。写真では,その葉っぱが見えないのですが…(宝立町,2023/04/10)


モミジイチゴ(紅葉苺) バラ科キイチゴ属 花期:4月~5月
落葉低木。イカリソウと同じ場所に咲いていました。林縁に見られます。モミジのような葉っぱの形をしています。また別名「黄苺」とも呼ばれるように,このあと6月頃には黄色い苺のような実がなります。
「キイチゴ属の中では一番おいしい」と「花しらべ」の解説にはありました。
写真の花は少し虫食いですので,改めてキレイなものを撮影したいと思っています。(宝立町,2023/04/10)


カキドオシ(垣通し) シソ科 花期:4月~5月
自宅のすぐそばにたくさん生えています。紫色のきれいな花だなと思っていると,蔓がドンドン伸びてきて,そこらあたり一面に広がってきますので,気になって調べたんでしょうね。たぶん。名前の由来も,垣根を通り越して延びることにあるらしいです。
乾燥させたものはレンセンソウ(連銭草)といって,糖尿病や尿路結石,小児のかんの薬効があるそうです。だから別名「疳取り草」。(宝立町,2023/04/14)


アケビ(木通) アケビ科 花期:4月~5月
ご存知,秋の風物詩。田舎に住んでいる人なら必ずや一度は食してみたことがあるんじゃないかな。タネが多すぎて困るけど,実の甘さは絶品。
春のころの姿は,大人になってから知りました。雌雄同株で,ぽつんと鮮やかな色で咲いているのが雌花です。雄花は集まっています。
英名は,Chocokate vine。vineというのはブドウの木のことだそうです。(宝立町,2023/04/24)


ウマノアシガタ(馬の足形) キンポウゲ科 花期:4月~6月
この時期,田舎の道を歩いていると道ばたに大変よく見かける黄色の花。多年草の植物です。
なんともけっけいな名前ですが,植物名の由来は,花の形が馬の足形に似ているからだそうすが,よく似た花はいっぱいありそうですね。
可愛い花ですが有毒なのでご注意を。汁液が付いただけで,皮膚炎を起こすことがあるそうです。
八重咲きのものはキンポウゲ(金鳳花)と呼ばれるそうです。(宝立町,2023/05/10)


アオマムシグサ(青蝮草) サトイモ科 花期:4月~5月
テンナンショウ属の植物。マムシグサに似ていますが仏炎苞(ぶつえんほう:ふたのような部分。一見,花びらのように見えますが、中央に突き出ているのが本当の花です)が緑色になっています。林などの湿った場所で見つかります。
この植物も有毒植物で,誤食すると口内炎・嘔吐を起こすことがあるそうです。お気を付けて。ただ,この姿を見ると,何かやらかしそうなので,触るのもはばかれますがね。(宝立町,2023/05/10)


チョウジソウ(丁字草) キョウチクトウ科 花期:4月~6月
この淡い青紫色の花って,なかなか見ないですよね。一度見たらずっと心に残る花です。わたしは10年ほど前に教えてもらってから,その場所へ行くと必ず探すようになりました。
名前の由来は,横から見る花の形が「丁」の字に見えるからだそうです。正面から見ると,まるで大文字草ですがね(^_^)。
この素敵な在来種。花言葉は「威厳」。ただし,北アメリカ原産のよく似た花もあるそうです。(三崎町,2022/05/27)


ノアザミ(野薊) キク科 花期:5月~8月
背丈が50㎝~120㎝くらいになる,草原に生える多年草。アザミの名前の由来は「花が美しいので近寄ると鋭いトゲにおどろく(=アサム)に因み,アサムが転訛してアザミになったとされる」(花しらべ)。
アザミ属の多くは秋に開花しますが,ノアザミは春から夏にかけて花を咲かせるので,すぐに分かります。また,総苞(花の下)を触るとちょっとべたつくので,ノハラアザミと区別できるようです。ちょっと触ってみてね~。ねちょねちょするよ。(三崎町,2023/06/14)


ノイバラ(野茨) バラ科 花期:5月~6月
野薔薇とも呼ばれる。日本・朝鮮半島原産の野生のバラ。日当たりのいい山野などに見られる。2㎝ほどの香りのある白い花を咲かせる。
園芸品種の薔薇の台木にも利用されるそうだ。
秋には,赤い実を熟す。
写真の葉っぱが照っているように見えるのは雨の後だから。(三崎町,2023/06/14)


ツルアリドウシ(蔓蟻通し) アカネ科 花期:6月~7月
地面を這う常緑つる性の多年草。薄暗い木陰に生えるので,この種がある場所は日当たりが悪いめったに上に延びず,地上をはっている。
特徴的なのは花の咲き方。枝の先端に必ず2つ並んで咲いている姿が可愛い。この花,実は子房の部分が一つなのである。だから,実もなかなか面白い形をしている。もし実を見つけたら,写真をアップするかも。(三崎町,2023/06/14)


ウツボグサ(靫草) シソ科 花期:6月~8月
日当たりの良い山地や草地などに自生する多年草。名前の由来の「ウツボ」というのは,弓矢を入れる入れ物=うつぼに似ているからだそうだ。しかし,その「うつぼ」を知らないと,かえって分からなくなりそうだけど(^^;)
茎が四角いのが特徴。花はご覧のように固まって咲く唇形花。若芽は食用になるらしい。(三崎町,2023/06/14)


カキラン(柿蘭) ラン科 花期:6月~8月
初めて見たときはなんかうれしくなった。この柿色を含んだグラデーションの花びらの色が,なんとも大人っぽくてすてきな蘭だ。
山野の日当たりがよく,でも少し湿っぽいところに自生している多年草。葉は互生し,葉身は長卵形,先は尖っている。
一目で好きになった蘭だ!(三崎町,2023/06/25)


ノギラン(芒蘭) キンコウカ科 花期:6月~8月
植物をよく知っている師匠から教えてもらった植物。ノギランという響きから,「ラン(蘭)」の仲間かと思ったけれど,姿はどうも蘭らしくない。しかも,キンコウカ科というよく知らない仲間らしい。
芒(のぎ)というのは,ススキ(芒・薄)の仲間に似ているから。また葉っぱが蘭に似ているから「ラン」と呼ばれているとか…,確かに…。
山地の草原に自生する多年草。(三崎町,2023/07/05)


ヤブコウジ(藪柑子) サクラソウ科 花期:7月~8月
サクラソウ科(旧ヤブコウジ科)の常緑小低木。高さ約30センチメートル。夏,葉の付け根に乳白色または淡紅色の小合弁花を総状につけ,球形の液果を結んで,冬,紅く熟す。山地に自生し,また,観賞用に栽培。アカダマノキ。ヤマタチバナ。深見草。漢名、紫金牛。〈[季] 冬 〉。物類称呼「紫金牛、からたちばな、…関東西国共に、―と云」(『広辞苑 第7版』より)
というわけで,わたしの家の庭にも,十両の名で咲いています。(三崎町,2023/07/05)


ヒメヤブラン(姫藪蘭) キジカクシ科 花期:6月~9月
紫色の可愛い花が印象的な,日本・朝鮮・中国原産の植物。日当たりのよい草地などに生える多年草。写真の花も,林縁に見つけました。ヤブランよりも小型なので「ヒメ」。
種子は4~6㎝の黒色になるそうです。(三崎町,2023/07/05)


キカラスウリ(黄烏瓜) ウリ科 花期:7月~9月
全国の人里近くの草藪などに生えているつる性多年草。家の裏のそんな場所に生えていました。よく似た植物にカラスウリがありますが,花の形や葉っぱの裏の特徴(毛があるかどうか)に違いがあります。またカラスウリはオレンジ色の実をつけますが,こちらは名前の通り黄色い実です。
夜しか咲かない(しかも1日で落ちてしまう)怪しい花が印象的ですね。(宝立町,2022/07/18)


オカトラノオ(丘虎の尾) サクラソウ科 花期:7月~8月
白くて小さな花が房状に咲き,動物のふさふさの白い尾っぽのように見えます。日当たりのいい山野に自生します。というわけで,名前の由来は「丘」に生え,花穂が虎の尾に似ているということ。耐寒性多年草。原産は,日本,朝鮮半島,台湾,中国など。
小さく白い花冠は5裂しています。(三崎町,2022/07/23)


オトギリソウ(弟切草) オトギリソウ科 花期:7月~8月
こんな雰囲気の黄色い花は,実によく咲いているので,なかなか正体は分かりません。一緒にいた植物に詳しいNPO会員(大先輩)に教えてもらいました。日当たりのいい山野に生える多年草です。確かに,林の中ではなく,道のすぐ傍に咲いていました。
漢字で書くと,弟切草。なんじゃ~ととても気になりますよね。
さて,名前の由来は…。
「鷹の傷を治す秘薬の秘密を洩らした弟を,鷹匠の兄が怒って切り殺し,その血しぶきが花や葉の黒点として残ったという平安時代の伝説に因む」(アプリ「花しらべ」より)
そうです。怖いな,これ。でも一度聞いたら忘れられない。
葉は対生。黄色の花弁には,ちょっとした黒い点が…これが血のあとなのか。止血の効果もあるそうですよ。
なお田んぼにもよく似た花が生えているそうですが,それはもう少し背丈が小さいようです。(三崎町,2022/07/23)


ギボウシ(擬宝珠) キジカクシ科 花期:6月~9月
擬宝珠(ギボシ)と言えば,橋や寺社の欄干にある飾りのこと。つぼみを横から見るとそう見えるというのだが…。ギボウシはギボウシ属の総称。写真の植物はオオギボウシだと思われる。葉っぱも大きいし,長~い茎の先に咲いているし。山林の日陰地に自生する多年草。4㎝くらいの可愛い花は白色~薄い青紫色。花言葉は「沈静」。そう,静かにみつめてください。(三崎町,2022/07/24)


ヘクソカズラ(屁糞葛) アカネ科 花期:7月~9月
名前がすごいですね。これ,葉や果実を潰すと,ほんとうに う●こ の匂いがします。しかもなかなか取れません。でも,一度でいいから経験しておくといいかも。花は小さくてきれいなんですがね。
左巻きのつる性多年草です。来年もあの匂いに出会えます。ただし,近づいただけでは匂いは分かりません。
別名は「早乙女花」。花の形から来ている名前だそうです。こっちで呼んであげましょう。(宝立町,2022/07/25)


ママコノシリヌグイ(継子の尻拭い) タデ科 花期:5月~10月
ずっと前から日本にあるからなのか,本当に変な前がついたものがあります。この種もすごいです。継子って育ての母親のこと。「尻を拭う」って,ウンチをしたあとでお尻を拭くことかな。
この種は,茎にも葉の裏にもたくさんのとげとげがあって,触ると怪我をするくらいです。こんなものを尻を拭かれたのでは,尻が血だらけになります。昔の人は,先妻の子の尻はこれで拭いておけばたくさんだってことで名前をつけたのでしょうかね。ほんと差別です!(宝立町,2022/08/03)


クサギ(臭木) シソ科 花期:7月~9月
これまたすごい名前がついています。なんせ「臭い木」ですからね。葉っぱをすこし触ってみましたが,そんなに臭くはありませんでした。ただ,揉んだりするとカメムシのニオイがするそうです。そりゃ臭いわ。
山林の林縁などにいち早く自生する(パイオニア植物・先駆植物)落葉低木です。
花がとても可愛くて,おしべがドカーンと出ているのがなんとも言えませんなあ。果実は黒くなります。(宝立町,2022/08/05)


クズ(葛) マメ科 花期:8月~10月
クズは,もうどうしようもないつる性の植物です。荒れ地や藪に自生しています。こいつが匍匐してくると,絶つのが難しいんですよね。
わたしの家の傍の旧能登線跡の周りにはこいつが蔓延っちゃって,草刈りさえもままなりません。在来種として大切にしたい気持ちもありますが…。「秋の七草」の一つであり,万葉集でも読まれている伝統的な植物なんですが。花は可愛いですね。葛餅のデンプンはこの植物の根から採るそうですが。
アメリカなどでは,日本から来た繁殖力の強い外来種としてとっても嫌われているそうです。(宝立町,2022/08/11)
万葉集より:ま葛延(は)ふ 夏野の繁く かく恋ひば まこと我が命 常(つね)ならめやも

ヒヨドリバナ(鵯花) キク科 花期:8月~10月
全国の山地の草原などに自生する多年草の植物。名前のヒヨドリは,「ヒヨドリが山から下りてきて鳴くころに開花する」からとか,「枯れた草はよく燃えることから〈火を取り〉が転訛した」という説があるらしい。
背丈は大きいのだと身長以上にもなるので目立ちますね。フジバカマ(葉が3裂する)によく似ているそうですが,ヒヨドリの葉は裂けません。(野々江町,2022/08/11)


ゲンノショウコ(現の証拠) フウロソウ科 花期:6月~10月
足下に小さな白い花が咲いていた。これがゲンノショウコ。漢字で書くと「現の証拠」。なにが「証拠」なのかというと,この植物は古来下痢止めに利用されていて,「ほら,やっぱりちゃんと効いたでしょ。現の証拠よ!」ということから付いたらしい。
果実が神輿の屋根に似ているよう(だから別名をミコシグサとも呼ぶ)だが,まだしっかり確かめてはいない。
葉っぱを手で揉んでみたが,嫌なにおいがずっと取れなかった。(宝立町,2022/08/12)


オミナエシ(女郎花) スイカズラ科 花期:7月~10月
黄色い小さな花が集まって咲いている。こんな雰囲気の植物はよく見るが…。
これはオミナエシという植物。あの「秋の七草」に出てくる植物である。
名前の由来は「花の色を栗飯にたとえたオンナメシ(女飯)が転化した」「枝が細く優しい姿から」という説(「花しらべ」より)があるらしいが,わたしは,後者を採用して憶えておきたい。(三崎町,2022/08/22)
万葉集より
をみなへし咲きたる野辺を行き廻り君を思ひ出た廻り来ぬ


オトコエシ(男郎花) スイカズラ科 花期:8月~10月
オミナエシのそのすぐ隣に,同じような形の白い花が咲いていた。これは女郎花に対して,オトコエシというらしい。なんとも短絡的な名付け方ではないか。まさか男郎花と書くのではないだろうな…と思って漢字変換してみたら,ちゃんと,「オトコエシ=男郎花」と出てきた。すげー。ただ,葉っぱの様子は似ているとは言えないな。
男にしたのは,女郎花よりも茎が太くて丈夫そうにみえるかららしい。うんうん,やはり,茎の太さで見るのがいいようだ。(三崎町,2022/08/22)


ボタンヅル(牡丹蔓) キンポウゲ科 花期:7月~9月
山野の日当たりのいい場所に自生するつる性の半低木。写真のボタンヅルは,斜面にある大きなツツジの木を覆うようにして生えていました。お~こわ。
名前は,牡丹のような葉をしていて蔓だから。葉は3出複葉。白い花が固まって咲くので大変目立ちます。
ただし,葉や茎を切ったときに出てくる汁は有毒で皮膚炎を起こすので要注意ですよ。(宝立町,2022/08/23)


ミズタマソウ(水玉草) アカバナ科 花期:7月~9月
日本原産の植物です。
右の写真は,上記ボタンヅルがあった辺りの日陰のところに,何株か生えていました。
名前の由来には,「球形の果実が水玉だから」「果実に付いた露が玉になるから」などがあるそうです。
小さい白い花の下に何やら毛のようなものが生えていますが,これはカギ状になっていて,果実ができると「くっつき虫」に変身するようです。(宝立町,2022/08/23)


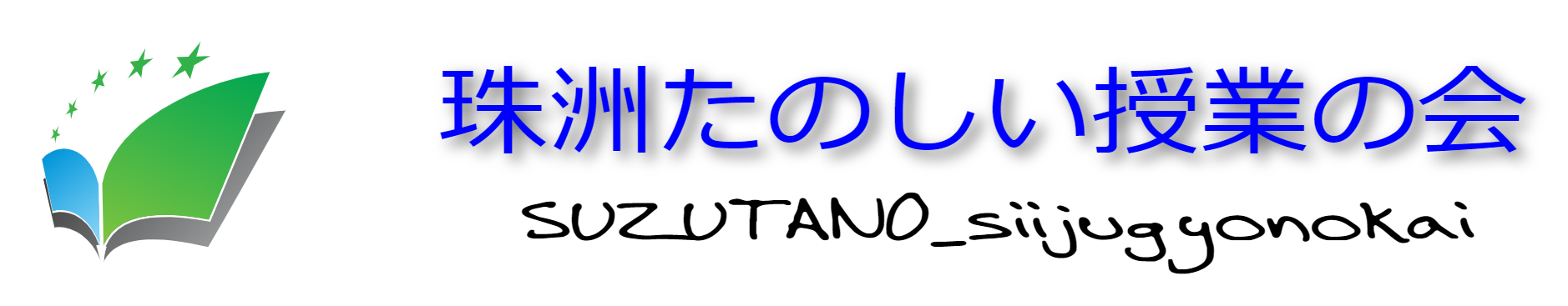
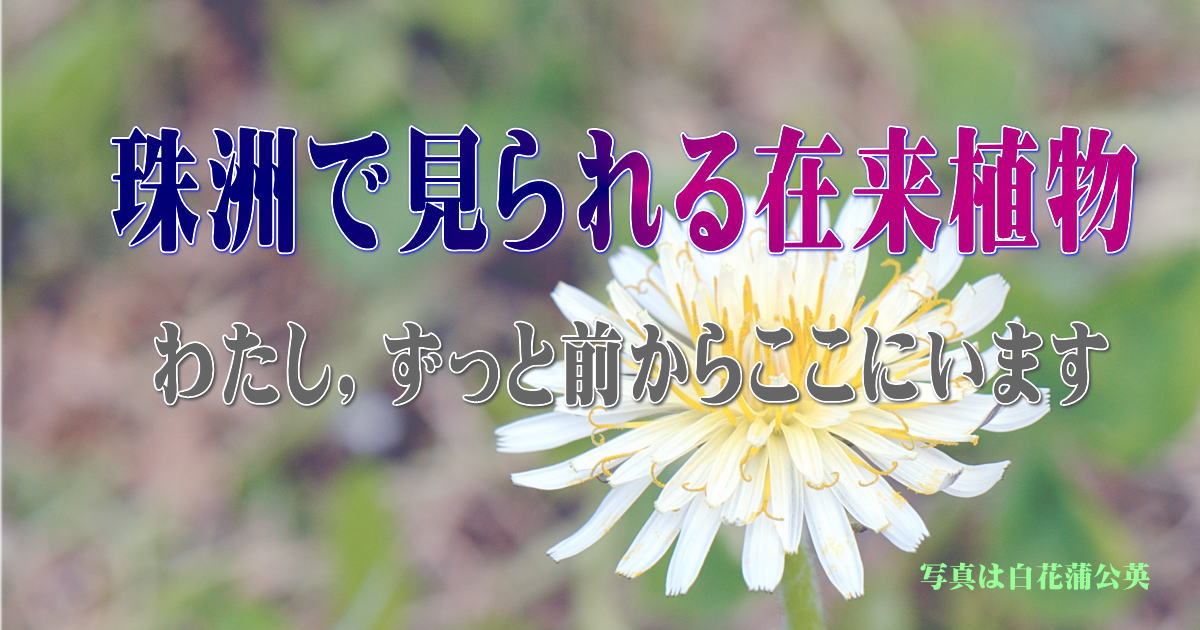


コメント