最果ての地・珠洲…なのに,ちゃんと外来種が増えていく。それだけ人間の行動範囲が広がっているということだろう。残念だけど,それが現実。とくに植物の場合は,はびこる外来種を除去しないで大切に育てている人もいる。花が大きくてきれいだから…という理由らしい。もともと園芸用に入ってきた種も多いようだから無理もない。わたし家の近くで見つけた外来植物(帰化植物)一覧を作っていこう。
「史前帰化植物」もこのカテゴリーに含めてあります。ただし,これらは,もう在来種と呼んでもいいほど,わたしたち日本人の生活に密接に関わっています。(例:イネ)
ヒメリュウキンカ(姫立金花) キンポウゲ科 花期:3月~5月
ここ数年で家の周りに大変蔓延るようになったタンポポのような植物。黄色い花(萼だが)が所狭しと咲く。葉っぱには光沢があり,なんともギラギラしていてわたしの好みではない。ごめんなさい。
ヨーロッパからシベリアの山地に分布していたという。名前はリュウキンカとついているのだが,リュウキンカの仲間ではなくキンポウゲ科。耐寒性で強い。夏は上部が枯れて夏眠?する。
根から抜こうと思っても,茎の中は空洞で弱く,すぐに茎が折れてしまい根っこが残る。だから,なかなか根絶できない。もちろん多年草なので,来年もまた咲く。それどころか,大量にできるタネは,風で運ばれて,わたしの家の庭にも畑にも入ってくる。このようにどこにでも潜り込むので,大変困っているのだ。
しかも,一見きれいな花なので,自分の家の道ばたにあっても駆除しない人も多いので,タネがどんどん広がるのである。あーあ。(2022.3.8,宝立町宗玄)


ハコベ(繁縷) ナデシコ科ハコベ属 花期:2月~10月
春の七草といえば?
「せり・なずな・おぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ これぞななくさ」と唱えられる。このうち「はこべら」というのがハコベのこと。また小鳥に餌として食べさせたりもするので,英名はChickweed=ニワトリの雑草と呼ぶ。
ハクベラは「波久倍良」として、平安時代の辞書類の『新撰字鏡』『本草和名』『和名類聚抄』などに見られるようだが,原産はヨーロッパだという。(三崎町粟津,2023/03/22)


オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢) オオバコ科 花期:11月~5月
もうすっかり日本の春の風物詩になってしまっている。原産地は西アジア。日本は極東なんだから…どうやって来たの?
「花調べ」によると,明治時代に東京で確認されたらしい。
本家本元のイヌノフグリは見たことがない。フグリは陰嚢のこと。実がそのように見えるというが…これは割と有名な話だ(2022.3.25,宝立町宗玄)


ミチタネツケバナ(路種漬花) アブラナ科 花期:2月~5月
ヨーロッパから東アジアに分布する越年草。上記のオオイヌノフグリと同じ場所に咲いていた。名前の由来は,道ばたに咲く,タネツケバナによく似た植物であるという意味。花は1~2㎝くらいで4枚の花びらをつけている。そういう意味では,ちゃんと十字架科(アブラナ科)なんだと思う。
こちらの方は道ばたのような乾いた場所が好きなようだが,タネツケバナは湿地に生えていて,茎にはもっとはっきりと葉っぱがつくことで見分けられる。おしべの本数も4本(ミチタネツケバナ)と6本(タネツケバナ)と,違うらしい。(2022.3.25,宝立町宗玄)

ツルニチニチソウ(蔓日々草) キョウチクトウ科 花期:3月~7月
わたしん家の近くでは,海岸に近くてちょっと開けた空き地で猛威を振るっている姿を見かける。
原産地は南ヨーロッパから小アジア。日本に入ってきたのは明治時代らしい。花言葉は「幼なじみ」だという。確かに,小さいときからよく見てきた花だ。花は紫色(5裂)で,しかもつる性で地面を覆い尽くすことが多いのでとても目立つ。だからグラウンドカバーにも使われたのだろう。それが野生化している。有毒(アルカロイド)なので気をつけよう。やっぱり多年草。日々草とは親戚(科は同じ)。(2022.5.9,宝立町鵜島)


シャガ(射干) アヤメ科 花期:3月~5月
ちょっと日陰の崖のような所に群生して生えています。わたしの家の近くでは,生えているところがお寺さんの墓場の裏の崖一面だったりするので,なんとなく昔から,ちょっと宗教がかった雰囲気を持っている花だなと思ってきました。
これが外来種だってことにビックリした方もおいでるかも。アプリ「花しらべ」によると,もともとは中国原産で古い時代に日本に入ってきたようです。名前と漢字の由来がややこしいらしいです。(2022.5.13,宝立町宗玄)


コメツブツメクサ(米粒詰草) マメ科 花期:4月~7月
子どもにも有名なシロツメクサよりも小さくて,黄色い花の咲くツメクサ(葉っぱもいわゆる三葉です)です。うちのまわりでは,5月に入ってから花が目立つようになります。原産はヨーロッパから西アジアで,1936年に東京で確認されたのがはじめてだそうです。これも立派な帰化植物。もうそこたら中に生えています。1年草らしいですが,なんか,地下茎で増えている雰囲気を持っていますよね。(2022.5.16,宝立町宗玄)


ハルジオン(春紫苑) キク科 花期:3月~6月
これもよく見る帰化植物。花の色は白~桃色があります(写真は,ほぼ同じ場所で撮影)。これとよく似た植物にヒメジオンがありますが,茎を折ってみるとその違いが分かります。ハルジオンは,茎の中が空洞です。それに咲く時期もちょっと遅くて6月~10月頃です。だから,今(5月)見ることができるのはハルジオンの方です。北アメリカ原産で,日本には大正時代に鑑賞目的で輸入されたそうです。これは多年草。(2022.5.15,宝立町宗玄)


ニワゼキショウ(庭石菖) アヤメ科 花期:5月~6月
小さくて可愛い花。私の経験上では,よく学校の運動場の草刈りができずに残っている部分にきれいに咲いていたのを思い出します。写真の花も空き地で見つけました。シロツメクサと場所を争っていました。この可愛いピンクの花も,残念ながら帰化植物です。原産は北アメリカ東部。明治20年頃に観賞用に日本に入ってきたそうです。名前の由来は庭に生える石菖のような葉っぱの植物。きれいな花は,1日しか咲きません。(宝立町宗玄,2022.5.25)


マンテマ ナデシコ科 花期:5月~6月
河原や海岸などの空き地に元気よく咲いています。きれいな小さい花なので一度目につくと,ついついのぞき込んでしまいます。ヨーロッパ原産で,江戸末期に観賞用として日本にやってきました。1年草なのですが,繁殖力が強いので,ちゃんと次の年にも同じような場所に咲いています。
右の写真は,家の下の砂浜へ降りるあたりにさいていました。完全な砂浜ではありません。(宝立町宗玄,2022.5.25)


コバンソウ(小判草) イネ科 花期:5月~8月
数週間前からいつものところにいつのもように群生をつくって自己主張をしてるコバンソウ。これも1年草なんですが,毎年ごらんのように群生しています。ほんと,小判のように見えますね。本物の小判は見たことないけど(^^;) 俵麦とも呼ばれるそうですが,そっちの方が似ているかな。これもまた帰化植物です。ヨーロッパの地中海沿岸が原産。明治時代に観賞用として輸入されたのがきっかけでここまで広がっちゃいました。(宝立町宗玄,2022.5.25)


ブタナ(豚菜) キク科 花期:5月~11月
これまた,ニワゼキショウ同様,学校の運動場のまわりによく生えています。子どもたちは,「首の長いタンポポあった!」と教室に持ってくることも度々でした。確かに,タンポポとよく似たところに生えていますし,地面の近くにある葉っぱもロゼットですね。タンポポではないけれども,タンポポの代わりに授業で使えます。名前の由来はフランス名(豚のサラダ)からだそうです(「花しらべ」より)。
これもヨーロッパ原産の帰化植物。1933年に札幌で確認されたのがはじめてらしいです。(野々江町亀ヶ谷池遊歩道,2022.5.26)


カモガヤ(鴨茅) イネ科 花期:5月~8月
こういう雰囲気(1mくらい)のイネ科の植物はよく見かけるので,なかなか区別がつきません。わたしは,植物をよく知っている方から教えてもらいました。晩春~夏にかけて写真のようなおしべを出して,花粉をまき散らし(否定的な表現!),初夏の花粉症の一因となっています。明治時代に牧草として輸入されたものが各地に広がったそうです。ヨーロッパから西アジア原産。名前の由来は,誤解からだそうです。本来なら「鶏茅」になるはずだったとか。(野々江町亀ヶ谷池遊歩道,2022.5.26)


コマツヨイグサ(小待宵草) アカバナ科 花期:4月~11月
北アメリカ原産の帰化植物。越年草。大正時代後期にやってきたそうです。乾いた砂地に生えています。自宅の近くでは,海岸の堤防の上あたりによく生えています。ほかの待宵草と比べて,背が低く花も小さいです。茎は頑張って斜めになっている(^_^)か,地上を這っています。4㎝ほどの4弁花をつけています。夕方に開花し,しぼんだ後は黄赤色になります。写真でもその色の変化が分かりますね。(宝立町南黒丸,2022.5.28)


えつねんそう【越年草】
『世界大百科事典・第2版』平凡社
北半球の温帯域に生育する草本植物で,秋に発芽し,冬を越して春になって開花結実枯死する冬緑一年草を一般には二年草という。ムギに伴った地中海地方原産の雑草に多く見られる生活型である。しかし,もし二年草を厳密に定義すれば,暦年で2年かかって生育開花枯死する植物(biennials)になるであろう。それに近いもの,例えば春に発芽,翌年の夏に開花し,秋に枯死するようなものは,オオマツヨイグサ集団の中の特別な個体に見られるが,多くはない。
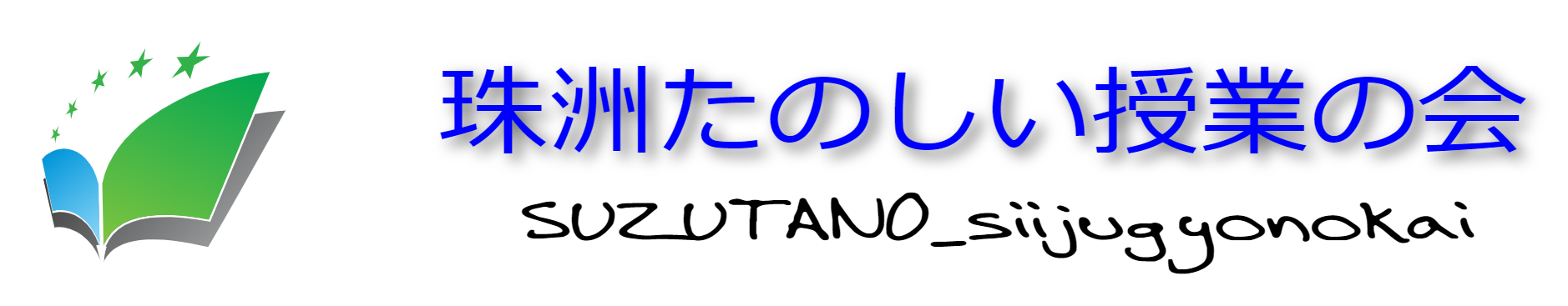



コメント