お久しぶりです。
サークル通信をお届けします。6月のサークルの例会は,選挙等のため中止せざるを得ませんでした。5月の会から2ヶ月あまりたちましたが,皆さんのクラスの方はどうですか?
今年度の僕は,これまでとは違う感じでの時間の使い方をしています。そこでこれからももしかしたらご迷惑をかけるかもしれないと思うので,ちょっと書いておきます。
一つは県の理科大会の事務局長の仕事です。本来,こういう仕事は一番苦手なのですが,成り行き上仕方なくなりました。これには結構いろいろなことに<気と時間>がとられます。この仕事は,今年度までなので,それまでのことです。
次に(…省略)。あと,学校では,相撲部の担当で何回か県内に試合があります(今年は東京へも行きます)。さらには,親としての仕事ですが,宝立ミニバス教室から今年は珠洲チームに参加することになり,そのための遠征やら何やらのこともでてきました。まったく,ここにきて私の自由時間はなしに等しいです。
そういうわけで,ボクの持っている時間は限られています。ボクに合わせていると,サークルの日取りもとれないことにもなりかねません。サークルの方は,ボクがいなくても例会を開いてもらってかまいませんので,宜しくお願いします。
実際,ここ数回,金沢サイエンスシアター研究会にも参加していません。参加して楽しくやりたいのは山々なのですがね。また「宝立小」や「珠洲たの」のホームページの更新もあまりできていません。
でも,理科大会やミニバスの仕事は通りすがりのものですので,2学期後半からは,また時間ができると思います。
とにかく,選挙前からここ数ヶ月が一番忙しいのですが,この夏休み期間中に大いに仕事をこなしたいと思っています。いろいろ迷ったあげく,今年は仮説の全国大会へは行かないことにしました。
4月号を発行していませんので,今回は2月分紹介します。
5月には,I小のKさんが新たに顔をのぞかせてくれました。よろしかったら,またサークルにきてください。
■4月の参加者(6名)
H.H(珠洲市T小) Y.N(珠洲市W小) M.O(珠洲市H小) M.S(珠洲市I小) K.H(珠洲市H中) T.M(内浦町M中)
■5月の参加者(5名)
H.H(珠洲市T小) Y.N(珠洲市W小) M.O(珠洲市H小) M.S(珠洲市I小) Y.K(珠洲市I小)
資料の紹介
1.『今月の本棚2000年4月号』 3ぺ M.O
ノートパソコンがきてからというもの,本からパソコンへとその自由時間の使い方が変化したので,しばらくは『今月の本』に紹介する本も少なくなりそうです。
●『平成サラリーマン川柳傑作選・4番打者』(講談社,1994,222ぺ,1000円)
●『平成サラリーマン川柳傑作選・5ツ星』(講談社,1995,224ぺ,1000円)
●玉川スミ著『ドドイツ万華鏡』(くまざさ出版社,1999,174ぺ,1500円)
●菊池聡著『超常現象の心理学』(平凡社新書,1999,190ぺ,660円)
●飯島弘文著『誰にも教えたくないWindows98/98SE メモリとシステム設定の秘密』(メディア・テック出版,1999,197ペ,1980円)
●『ステップ図解・Windows98でネットワーク』(ナツメ社,1999,223ペ,2000円)
どうも完璧に趣味の本になってしまいました。その中でも,菊池聡著『超常現象の心理学』(平凡社新書)がおすすめかな。血液型性格判断,そろそろやめようよ。
2.学級通信『続・気球』№43,45,46 10ぺ M.O
No.43は「カナリアという言葉はスペイン語かポルトガル語か」ということを旺文社に聞いたときの返事をまとめたものです。国語の時間で外来語を調べていたときに,同じ旺文社の会社でありながら,辞典によって「スペイン語」とするものと「ポルトガル語とするものがあったので疑問に思いメールで質問したのです。
No.45は《ゴミと環境》の授業記録(第11時間目)です。珠洲市の資源化率を予想する問題と,子どもたちの授業後の感想文を載せました。
No.45は最終号です。「卒業する君たちへ」と書いてみました。はじめは何も書かないでおこうと思ったのですが,突然思い立って学校へ行き,10時頃までに書き上げて印刷して次の日渡しました。ちょっと思い入れ過ぎの文章になって,今読むと恥ずかしいなあ。
3.学級だより『とれいん 20プラス1』№25,26 12ぺ M.S
№25は,《電池と回路》の授業評価と感想文です。対象は小学3年生。感想を一例紹介します。
○電池のことがすごくよくわかりました。いろいろな電池やソケット,V,回路,それにコンデンサもすごく分かりました。うちでもいろいろな電池をさがして,もっともっとしりたいです。(M)
小学3年生でも(だから)もっともっと知りたくなるのですね。
№26は『あるはれたひに』を授業で呼んで聞かせたという記録です。ボクもこの本を小6の子供らに呼んで聞かせましたが,大変好評でした。絵本の力はすごい(もちろん,内容がいいものに限りますが)。
この授業のあとで子どもたちから「先生,これって道徳の授業なんじゃないがあ」と聞かれて,びっくりしたとSさんは言います。「私は単純にあの絵の中のおおかみとやぎの関係がおもしろいなあ」と思って授業に呼んであげただけなのに,子どもたちは「友達は大切だ」とか感想に書いていて,なるほどと思ったというわけです。う~ん。
4.『1年道徳指導案』と記録 5ぺ K.H
サークルの定番道徳教材『忘れられないご馳走』を使った中1での授業案です。
学級のメンバーが少人数なので,なかなか意見のぶつかり合いもないようですが,話の展開がおもしろいので,子どもたちはリラックスして授業を受けていたようです。ただ,指導案の中に「仮説実験授業から取り入れた」とあるのは,間違いです。仮説実験授業研究会はこういうミニプランも開発・研究しますが,それはあくまでも「楽しい授業を成り立たせるための指導案・授業プラン」であり,仮説実験授業とは言いません。仮説実験授業というのはもっともっと狭い意味なので,ご注意ください。
5.学級通信『BEGIN』№1,3 4ぺ K.H
中学1年生の通信です。
担任から,新1年生に期待したいこと-『元気で毎日を過ごしてほしい』『一人はみんなのために みんなは一人のために』だそうです。
ボクも最近は,「○○に期待したいこと」という文章を必ず学級通信に書くようになりました。学年はじめにしっかり言っておこくとは,けじめを持たせる意味でも結構大切なことのように思いますが,みなさんは,どう思われますか?
6.学級通信『ひだまり』№1 2ぺ M.S
「はじめまして」と1年おいての持ち上がりの6年生を担任。
新居さんの「人間を言います」をもじって,班ごとに「6年生を言います」を考えてもらったそうです。さすが一度担任したかいがあります。そこででてきたのは「6年生はよく考えて行動します」「6年生は楽しく過ごします」など6つ。
こういうのも,なんとなく遊び感覚で決めておくといやらしくなくていいですね。学級目標っていうと,「いい子が教師向けの意見を言って終わり」ってことがママありますから。
7.『悩んでしまった・・・』 5ぺ M.S
清水哲さん(元PL学園の野球選手が,大学時代,ヘッドスライディングを試みた際,首の骨を骨折。その後の生き方がなかなか半端じゃない)の生き方そのものを教材として授業にかけたのだが,はたと悩んでしまった-というSさんの思いが語られました。
授業後,子どもたちは「清水さんは,かわいそうだ」と感想を書きました。しかし,こんな思いをいだかせただけでいいのだろうかと悩んだ訳です。
今回,授業をしながら,Sさんは清水さんと電子メールで何度か会話を交わしています。それだけに,よけいに「通り一遍の授業」では,腑に落ちないものが残ったのでしょう。
このサークル後に,事態は急展開します。この後のことについては,次回のサークルに本人がじっくり語ってくれると思いますので,ご期待ください。
8.『Intel Play QX3 Microscope』 紹介 M.O
パソコン月刊誌『Oh! PC』3月号に<Intel Play QX3 Microscope>という顕微鏡の紹介がありました。「静止画だけでなく動画の撮影もできるUSB接続対応のデジタル顕微鏡」と紹介されています。それを読むと,まだ正式な日本語版はでていないのですが,パソコン画面上での操作は簡単そうです。
というわけで,ボクはインターネットで東京のお店に注文し,輸入品を手に入れることができました。1万5000円ほどですので,おもちゃのようなものですが,それでもいろいろと遊べそうです。
予定では6月中に日本語版の製品が出ると言っていました(日経パソコン誌)ので,いまじゃあ,日本語版が手に入るはずです。これもどんな使い道があるか,子供たちと一緒に探ってみたいものです。
昨年の秋ぐらいから,デジカメが行方不明となっています。今となっては,見つかるはずもなく期待もしていません。モノの整理の仕方がいかに悪いかですねえ。そろそろ我慢の限界か。一つほしくなってきました。
デジカメ・エコログ・QX3など,なかなかおもしろい周辺機器が出てきて,パソコンの新しい使い方が出来そうです。またいろいろと情報交換が出来たらいいですね。
なお,次回のサークルには,ボクは5時過ぎまでしかおれません。5時30分から次の会がありますので,あしからず。
珠洲たの通信・写真編

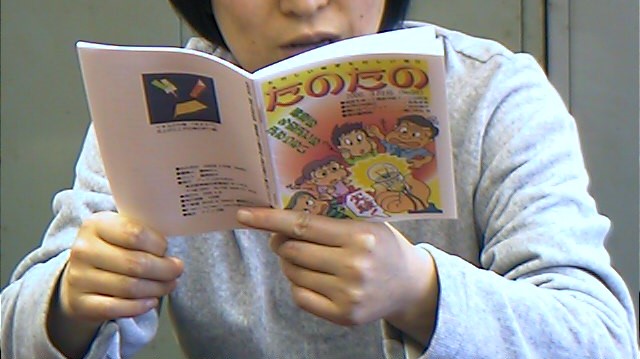
この日にサークルで紹介されたのが,「静止画だけでなく動画も撮影できるUSB接続対応のデジタル顕微鏡」と雑誌にコマーシャルされていた顕微鏡の実物です。製品名は「Intel Play QX3 Microscope」というそうです。
この顕微鏡の存在を知ったのはパソコン月刊誌『Oh!PC 3月号』です。半分おもちゃのようなものですが(値段も1万5000円くらい),それでも,気軽に顕微鏡の像をデジタル化できるのはうれしいです。少し中身を紹介します。
windows98に対応。接続はUSBのみです。顕微鏡の倍率は10倍,60倍,200倍の3段階から選択できます。試料の照明方法は,反射光で見る方法(ライトスコープと同じ)と,透過光で見る方法(普通の学校にある顕微鏡と同じ)の両方があります。それも,パソコン上から切り替えることが出来るので大変便利です。
サークルの時には,まだ日本語版が出ていなくて,インターネットで取り寄せた輸入品を紹介しましたが,その後,日本語対応の製品も出て,Mさんも手に入れたそうです。
夏休み,これを使って,何が出来るか考えたいなあ。
右の写真は『たのたの』を読んで紹介するSさんです。『たのたの』のことは,仮説実験授業研究会の人なら知っていると思いますが,薄いご覧のようにとっても薄い本なのですが,中身がなかなか面白いのです。この本に取り上げられてから仮説社の『たのしい授業』に掲載された記事もたくさんあります。
レポートの交流だけでなく,それぞれのメンバーがいろいろなところから得た情報を交流するのもサークルの楽しさです。自分自身のアンテナは限られていますので,こうやって友達のアンテナに引っかかった情報を交流することで,生活が豊かになります。
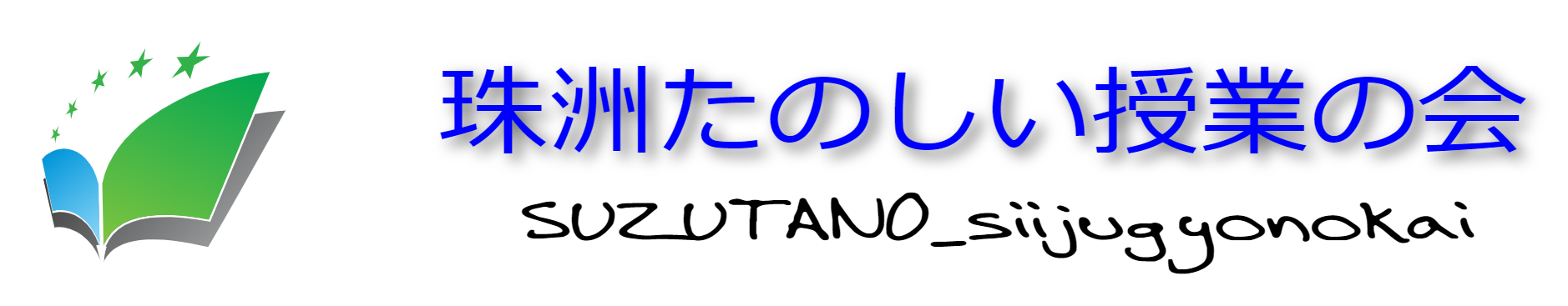

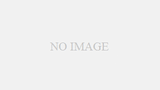
コメント